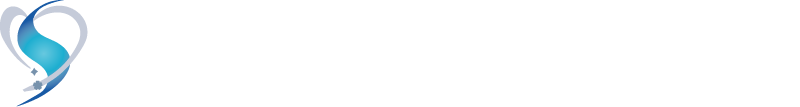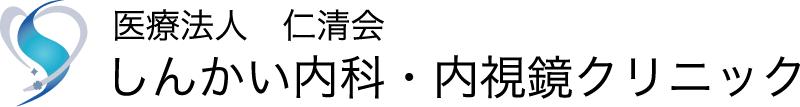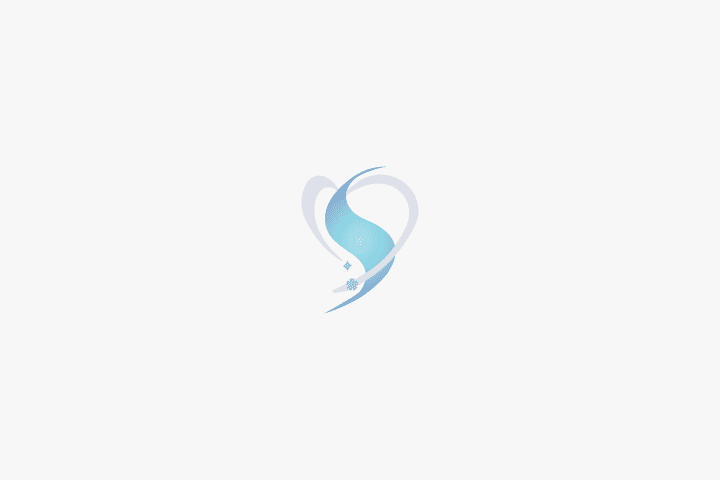2025年10月23日
胃がん検診 ― バリウム検査と胃カメラ検査の違い ―
日本では胃がんはピロリ除菌などによりその罹患者・死亡者数は少なくなってきたものの、依然として命を落とす方は存在する疾病です。一方で早期に発見して治療することで、命を守ることができるがん」腫でもあります。胃がん検診には主に「バリウム検査(胃部X線検査)」と「胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)」の2つの方法があります。それぞれに特徴があり、目的や体調に応じた選択が大切です。ここでは両者の違いと、当院でおすすめしている胃カメラ検査の利点について詳しくご紹介します。
■ バリウム検査とは
バリウム検査は、造影剤(バリウム)を飲んで胃の内部をX線で撮影する検査です。胃の形や粘膜の凹凸、変形などを観察することができます。全国の自治体健診や職場健診で広く実施されており、比較的短時間で行えるのが特徴です。
検査時間はおおよそ10分程度で、検査後の安静や鎮静は不要です。放射線による影響はごくわずかで、通常の健診レベルであれば安全に受けられます。
ただし、バリウム検査にはいくつかの注意点があります。まず、胃の粘膜を直接見ることができないため、小さな早期がんや平坦ながん、色調の変化を伴う病変などは見逃されることがあります。
また、バリウムが腸に残りやすく、腸閉塞を起こしたり、まれに誤嚥を起こしたりすることもあります。私はもともと外科医でしたのでこれまでに何人かバリウム腸閉塞や腸穿孔を手術した経験もあります。さらに、もし異常が見つかった場合は、確定診断のために胃カメラでの再検査が必須となります。
したがって、バリウム検査はスクリーニングとしては有用ですが、精密な観察には限界があります。
■ 胃カメラ検査とは
胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)は、口または鼻から細い内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察する検査です。医師が実際に粘膜の状態をリアルタイムで確認できるため、非常に精度の高い検査といえます。
炎症やびらん、ポリープ、潰瘍、早期がんなど、わずかな粘膜変化を見つけることが可能です。さらに、異常があればその場で組織の一部を採取して病理検査を行える点も大きなメリットです。ピロリ菌感染の有無を調べることもでき、将来の胃がんリスク評価にもつながります。
以前は「胃カメラは苦しい」という印象がありましたが、近年は大きく改善しています。当院では、より細い経鼻内視鏡を採用しており、口から挿入する場合に比べて嘔吐反射が起きにくく、会話も可能です。
また、希望される方には鎮静剤(静脈麻酔)を使用し、眠った状態で検査を受けていただけます。これにより、ほとんど苦痛を感じることなく、安全で精度の高い検査が可能となります。
■ 発見率と信頼性の違い
複数の臨床研究で、胃カメラは胃がんの発見率がバリウムの約2〜3倍と報告されています。
バリウム検査では、凹凸や形の異常から間接的に病変を推測しますが、胃カメラは実際の粘膜を直接確認できるため、早期の段階でも発見が可能です。特に、ピロリ菌感染による慢性胃炎や萎縮性胃炎など、胃がんの前段階ともいえる状態を評価できるのは胃カメラだけです。
日本の胃がん検診ガイドラインでも、50歳以上では胃カメラによる検診を優先的に推奨する流れが広がっています。
また、一度胃カメラで異常がないと確認できれば、その後のリスク評価や検査間隔の目安も立てやすくなります。
■ 当院での取り組み
しんかい内科・内視鏡クリニックでは、「できるだけ楽に・正確に・安全に」検査を受けていただくことを重視しています。
経鼻内視鏡による苦痛の少ない検査、鎮静下でのリラックスした検査のほか、最新の高画質内視鏡システムを導入し、微小ながんの早期発見に努めています。
検査後は画像を一緒に見ながら丁寧に説明し、必要に応じて治療や経過観察の計画をご提案します。
胃の不快感や痛みがある方はもちろん、健診で「要精査」と言われた方、ピロリ菌が陽性だった方も、どうぞお気軽にご相談ください。
バリウム検査は手軽で受けやすい反面、精度には限界があります。
一方の胃カメラは、多少手間はかかりますが、がんを早期に発見できる最も確実な方法です。
しんかい内科・内視鏡クリニックでは、「苦しくない胃カメラ」を目指し、安心して受けられる環境を整えています。
定期的な胃カメラ検診で、胃の健康を守りましょう。